六書と書体の変遷表
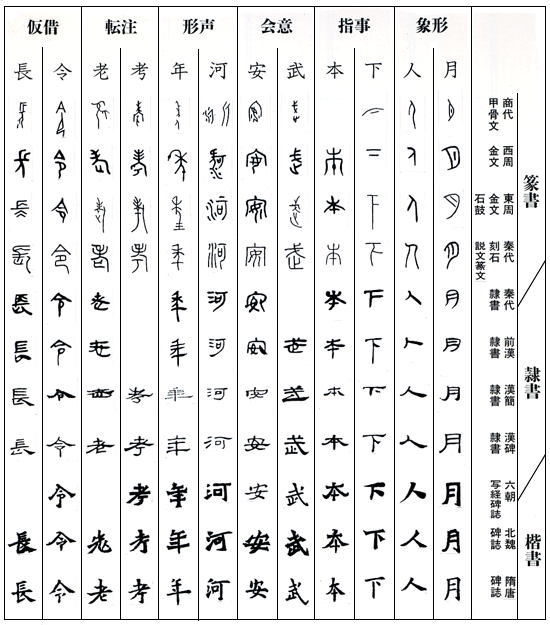
漢字の成立
漢字は、伝説によれば、
現在確認できる最古の漢字は、殷(または商)の後期(紀元前一三〇〇1300〜一〇〇〇1000年ごろ)のものである。殷時代には、亀の甲羅や獣の骨などに生じさせたひび割れの形から吉凶を判断し、その内容や出来事の結果などを併せて刻みつけた。そうした文章に用いた文字を「甲骨文字」という。
それより古く、たとえば
漢字は甲骨文字から現在まで、時には大きな変革をしつつ、発展してきた。その過程で、篆書・隷書・楷書・行書・草書が生み出された。
篆書には、甲骨文字、金文、
隷書には、篆書の筆画をとどめた秦隷(古隷とも)のほか、前漢の武帝末年から後漢の時代の、見事な波発の備わった扁平な字形をした漢隷(
草書は、隷書の補助書体として前漢末にはすでに完成していた。そして、後漢には大流行したが、末期には廃れてしまった。こうした隷書時代の草書を
草書に代わる隷書の補助書体として、後漢末には行押書と呼ばれるものが通行した。これは今日の行書の基に当たるものである。
楷書は、初め真書または正書とも呼ばれ、行書を正しく整えて、書写の楷模(手本)となる書体として生じた。
同じ楷書でも、一つの字に複数の書き方をもつものがある。跡と蹟、聡と聰、略と畧、剣と剱釼など、字音と字義は同じだが、字形が異なる場合が少なくない。このうち、標準的なものを正字、それ以外を異体字という。これは、漢代から初唐に至る、隷書から楷書への移行過程で生じた、さまざまな楷書体が、統一されないまま用いられてきたことを反映している。
異体字には字画を簡略にした略字も含まれるが、その略字が通用字体となる場合もある(中国では簡体字が用いられている)。それに加えて、楷書体と活字体の対応関係も必ずしも単純ではない。そのため、渡辺の「辺」「邊」「邉」「 」のようにさまざまな楷書体がある場合、字形の問題を一層複雑にしている。
」のようにさまざまな楷書体がある場合、字形の問題を一層複雑にしている。
漢字の構成原理については、「説文解字」(後漢の許慎著)で
象形は、事物の形状を描き象ったもので、「日・月・人・馬」などがこれにあたる。
指事は、象形字に符号を付けて、抽象的な概念を表したもので、「上・下・本・末」などである。
会意は、二つあるいは二つ以上の字を合成したもので、[武・信・男・安」などがこれである。
形声は、事物の種類を表す意符(義符)と、発音を表す声符(音符)からなるもので、これには「江・河・年・遠」などがある。
転注は、種々の解釈があり定まらないが、許慎の説では、意義の同じ字を一類に帰属させ、統一した部首として互いに意味が同じで、相互に注解できるものとする。たとえば、「考-老」の類をいう。
部首
漢字という文字体系を、字形を構成する同一もしくは類似する要素に着目して分類した場合、いくつかのグループに分けられる。そうした、それぞれのグループの代表となる字もしくは構成要素を部首という。部首はそれに属する漢字のグループに共通する根幹的な意味を表すもので、部首による分類はほぼ意義による分類に近いものとなる。たとえば「話・謝・譬」などの「言」を部首とする漢字の一群は字形上「言」という要素によって一部門をなすが、それはそれぞれの漢字が意味の上で言葉と関係するからでもある。このような部首の性格は漢字の大部分が形声と会意による造字であり、特に形声による造字が漢字総数の八割ほどを占めていることに由来する。
「説文解字」は部首分類による最も古い字書で、「一・二・示・三」から「酉・ ・戌・亥」に至る五四〇540の部首を立てている。また、日本の古辞書に大きな影響を与えた顧野王の「玉篇」(五四三543年)も五四二542の部首に分けているが、これらはやや細かすぎて、単に検索だけのための構成要素も多く含んでいる。
・戌・亥」に至る五四〇540の部首を立てている。また、日本の古辞書に大きな影響を与えた顧野王の「玉篇」(五四三543年)も五四二542の部首に分けているが、これらはやや細かすぎて、単に検索だけのための構成要素も多く含んでいる。
これに対して「康煕辞典」(一七一六1716年)は「字彙」(一六一五1615年)に従って二一四214の部首に分けている。近代以降の日本の漢和辞典は分類上これを範とし、だいたい二二〇220前後に分けるのが一般的である。ただ、それでも意味とは無関係に構成要素の外形上の類似だけによって一つの部首にまとめる場合が依然として含まれている。ちなみに、日本の部首分類による古字書では、「新撰字鏡」が約一五三153、「類聚名義抄」が一二〇120の部首をたてている。
部首名の「連火(→れっか)」「三水点(→さんずいへん)」「之遶(→しんにゅう)」「立心(→りっしんべん)」などは「新撰字鏡」にすでに見えており、こうした偏旁冠脚の名称は早くから慣用されていたことが知られる。
日本の漢字
四世紀後半から五世紀初めごろには、日本と朝鮮半島との交流が一段と活発になり、渡来人たちによって本格的に漢字表記が移入され、職業的に書記活動に携わる者(のちには「
- 一、漢文によって、ある事柄を書き記す
- 二、漢字の音だけを借りて、固有の名詞を表記する
一は、表語文字である漢字の本来的な用法で、意味概念を表出するものである。二は、漢字本来の意味とはかかわりなく漢字の読みを用いて書き表す用法で、固有名詞や日本語特有の意味を有する語を原音に従ってなるべく忠実に音訳したのである。二のような用法は万葉集に多く見えるところから、「万葉仮名」と呼ばれている。また、漢字を「
漢字を移入した当初は、日本語とは無関係に、ある事柄を中国語つまり漢文で書き記していたが、やがて日本語を基盤として漢文を利用した意訳へと推移する。そして、漢文で文章表記される機会が増えてくると、その漢字を日本語に翻訳して理解しようとするようになった。たとえば「山」は日本語では<yama>の意味であることから、「山」と言う漢字自体を[yama]と訓むのである。このような漢字と「訓」との結びつきは当初は流動的であったが、徐々に慣用的に安定した結合となり、音に加えて訓をもつことによって漢字は日本語表記に定着していった
中国語にその意味概念がない場合は、万葉仮名によって音節表記するほか、漢字の構成原理に倣って日本で漢字を作って表すこともあった。このような日本製の漢字を「国字」(和字)という。そのほとんどは六書でいえば会意に相当するものである。例えば、身の美しさを「
万葉仮名は古くは音によるものだけであったが、訓が定着するようになると、訓による万葉仮名も用いられるようになる。前者を音仮名、後者を訓仮名と呼ぶ。そうした上代の万葉仮名の用法として注目されるのが上代特殊仮名遣いである。例えば、ミ(三・御)やカミ(上・髪)のミには「弥・美」などを用い、ミ(身・実・箕)やカミ(神)のミには「未・味・微」などを用いるというように、現代では同じ音節を表すように見える万葉仮名が語によって使い分けられていた。その使い分けの見える音節は、キケコソトノヒヘミメヨロ、およびその濁音のギゲゴゾドビベ(古事記ではモが加わる)であるが、この二類の別を甲類、乙類と呼び、「弥・美」などの類をミ甲類、「未・微」などの類をミ乙類という。この区別は発音の違いに基づくもので、奈良時代末期まではほぼ保たれていた。前述の音節のほか、ア行のエとヤ行のエも区別されていた。
清濁の書き分けもかなり厳密であり、清音仮名、濁音仮名とも名づけることができるものも認められる。しかし、清濁の対立は特に語頭においては存在しないなど、音韻論的には必ずしも明瞭な対立ではなかった。従って、実用的な文章では清音仮名が濁音節に用いられることも多く、徐々に万葉仮名が整理されていった。それとともに字体も書きやすいように簡略化されてゆくが、それは、万葉仮名を書きくずすという草体化と、字形の一部を省略するという略体化の方向をとり、平仮名、片仮名を生み出したのであった。
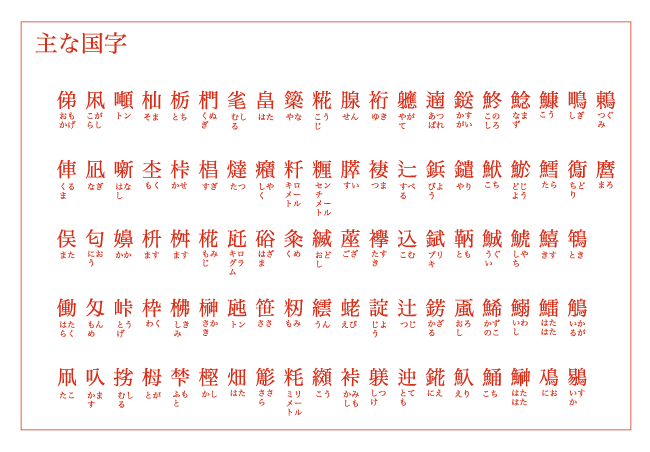
主要万葉仮名表
黒字は音仮名、赤字は訓仮名
- あ
- 阿
- 安
- 婀
- 鞅
- 吾
- 足
- い
- 伊
- 夷
- 怡
- 以
- 異
- 已
- 移
- 易
- 射
- 胆
- う
- 汙
- 有
- 宇
- 于
- 羽
- 烏
- 紆
- 禹
- 雲
- 菟
- 鵜
- 卯
- 得
- え
- 衣
- 愛
- 依
- 亜
- 哀
- 埃
- 榎
- 荏
- 得
- お
- 意
- 於
- 隠
- 飫
- 淤
- 憶
- 応
- 磤
- 乙
- か
- 加
- 可
- 賀
- 珂
- 哿
- 河
- 迦
- 訶
- 箇
- 嘉
- 架
- 伽
- 歌
- 舸
- 軻
- 柯
- 介
- 甲
- 髪
- 鹿
- 蚊
- 香
- が
- 何
- 我
- 賀
- 河
- 蛾
- 餓
- 峨
- 俄
- 鵝
- き甲
- 支
- 吉
- 岐
- 伎
- 棄
- 枳
- 企
- 耆
- 祗
- 祁
- 寸
- 杵
- 来
- き乙
- 貴
- 紀
- 幾
- 奇
- 騎
- 綺
- 寄
- 記
- 基
- 機
- 己
- 既
- 気
- 城
- 木
- 樹
- ぎ甲
- 藝
- 祇
- 岐
- 伎
- 儀
- 蟻

- ぎ乙
- 疑
- 宜
- 義
- 擬
- く
- 久
- 玖
- 口
- 句
- 群
- 苦
- 丘
- 九
- 鳩
- 倶
- 区
- 勾
- 矩

- 衢
- 寠
- 屨
- 君
- 来
- ぐ
- 具
- 遇
- 求
- 隅
- 虞
- 愚
- け甲
- 祁
- 家
- 計
- 鶏
- 介
- 奚
- 谿
- 価
- 結
- 稽
- 啓
- 兼
- 監
- 険
- 異
- け乙
- 居
- 気
- 既
- 該
- 戒
- 階
- 開
- 愷
- 凱
- 概
- 穊
- 毛
- 食
- 飼
- 消
- 笥
- げ甲
- 下
- 牙
- 雅
- 夏
- 霓
- げ乙
- 義
- 宜

- 礙
- 皚
- こ甲
- 古
- 故
- 高
- 庫
- 祜
- 姑
- 孤
- 枯
- 固
- 顧
- 子
- 児
- 籠
- 小
- 粉
- こ乙
- 己
- 許
- 巨
- 居
- 去
- 虚
- 忌
- 挙
- 莒
- 拠
- 渠
- 興
- 木
- ご甲
- 胡
- 呉
- 後
- 虞
- 吾
- 誤
- 悟
- 娯
- ご乙
- 其
- 期
- 碁
- 凝
- 語
- 御
- 馭
- さ
- 佐
- 沙
- 作
- 左
- 者
- 柴
- 娑
- 紗
- 瑳
- 磋
- 舎
- 差
- 草
- 酢
- 散
- 作
- 狭

- ざ
- 射
- 蔵
- 邪
- 奢
- 社
- 謝
- 座
- 装
- 奘
- し
- 斯
- 志
- 之
- 師
- 紫
- 新
- 四
- 子
- 思
- 司
- 資
- 茲
- 芝
- 詩
- 旨
- 寺
- 時
- 指
- 此
- 次
- 死
- 偲
- 事
- 詞
- 絁
- 矢
- 始
- 尸
- 試
- 伺
- 璽
- 辞
- 嗣
- 施
- 洎
- 信
- 色
- 式
- 磯
- 為
- じ
- 自
- 士
- 慈
- 尽
- 時
- 寺
- 仕
- 弐
- 児
- 尓
- 珥
- 餌
- 耳
- 茸
- 下
- す
- 須
- 周
- 酒
- 洲
- 州
- 珠
- 主
- 数
- 素
- 秀
- 輸
- 殊
- 蒭
- 酢
- 簀
- 樔

- 渚
- 為
- ず
- 受
- 授
- 聚
- 殊
- 孺
- 儒
- せ
- 勢
- 世
- 西
- 斉

- 細
- 制
- 是
- 剤
- 瀬
- 湍
- 背
- 脊
- 迫
- ぜ
- 是
- 筮
- 噬
- そ甲
- 蘇
- 宗
- 祖
- 素
- 泝
- 十
- 麻
- そ乙
- 曾
- 所
- 僧
- 増
- 則
- 贈
- 諸
- 層
- 賊
- 衣
- 背
- 其
- 苑
- 襲
- ぞ甲
- 俗
- ぞ乙
- 叙
- 存
- 序
- 賊
- 鐏
- 茹
- 鋤
- た
- 多
- 太
- 大
- 他

- 柂
- 哆
- 駄
- 党
- 田
- 手
- だ

- 太
- 大
- 驒
- 娜
- 嚢

- ち
- 知
- 智
- 恥
- 陳
- 致

- 笞
- 池
- 馳
- 道
- 千
- 乳
- 路
- 血
- 茅
- ぢ
- 遅
- 治
- 地
- 膩

- 尼
- 泥
- つ
- 都
- 豆
- 通
- 追
- 頭
- 菟
- 途
- 屠
- 突
- 徒
- 覩
- 図
- 川
- 津
- づ
- 豆
- 頭
- 逗
- 図
- 弩
- 砮
- て
- 氐
- 提
- 天
- 帝
- 底
- 堤
- 諦
- 題
- 手
- 代
- 価
- 直
- で
- 提
- 代
- 伝
- 殿
- 田
- 低
- 泥

- 耐
- 弟
- 涅
- と甲
- 刀
- 斗
- 都
- 土
- 度
- 覩
- 妬
- 杜
- 図
- 屠
- 塗
- 徒
- 渡
- 戸
- 聡
- 門
- 利
- 礪
- 砥
- 速
- 疾
- と乙
- 止
- 等
- 登
- 騰
- 苔
- 台
- 縢
- 藤

- 得
- 鳥
- 十
- 跡
- 迹
- 常
- ど甲
- 度
- 渡
- 土
- 奴
- 怒
- ど乙
- 杼
- 騰
- 縢
- 藤
- 特
- 耐
- 廼
- な
- 那
- 奈
- 乃
- 寧
- 儺
- 娜
- 南
- 難
- 名
- 魚
- 中
- 菜
- 七
- 莫
- に
- 尓
- 迩
- 仁
- 日
- 二
- 而
- 尼
- 耳
- 人
- 珥

- 弐
- 丹
- 荷
- 煮
- 似
- 瓊
- ぬ
- 奴
- 怒
- 努
- 濃
- 農
- 沼
- 宿
- 寐
- 渟
- ね
- 尼
- 禰
- 泥

- 年
- 涅
- 念
- 根
- 宿
- の甲
- 努
- 怒
- 奴
- 弩
- 野
- の乙
- 乃
- 能
- 廼
- 笶
- 荷
- 箆
- は
- 波
- 播
- 幡
- 芳
- 婆
- 破
- 方
- 防
- 八
- 房
- 半
- 皤
- 薄
- 伴
- 泊
- 簸
- 巴
- 絆
- 泮
- 羽
- 葉
- 歯
- 者
- ば
- 婆
- 伐
- 麼
- 魔
- 磨
- 縻
- ひ甲
- 比
- 卑
- 必
- 臂
- 賓
- 嬪
- 毗
- 譬
- 避
- 日
- 檜
- 氷
- 飯
- ひ乙
- 非
- 斐
- 肥
- 悲
- 飛
- 被
- 彼
- 秘
- 妃
- 費
- 火
- 樋
- 干
- 乾
- 簸
- び甲
- 毗
- 鼻
- 妣
- 婢
- 弥
- 弭
- 寐
- び乙
- 備
- 肥
- 媚
- 眉
- 縻
- ふ
- 布
- 不
- 敷
- 富
- 甫
- 賦
- 府
- 否
- 負
- 符
- 輔
- 赴
- 浮
- 経
- 歴
- ぶ
- 夫
- 父
- 部
- 扶
- 歩
- 矛
- 騖
- へ甲
- 平
- 弊
- 霸
- 幣
- 敝
- 陛
- 遍
- 返
- 反
- 弁
- 蔽
- 鞞
- 鼙
- 部
- 辺
- 重
- 隔
- へ乙
- 閇
- 倍
- 拝
- 沛
- 陪
- 背
- 杯
- 俳
- 珮
- 戸

- 綜
- 経
- べ甲
- 弁
- 便
- 別
- 謎
- 部
- べ乙
- 倍
- 陪
- 毎
- ほ
- 富
- 菩
- 保
- 宝
- 本
- 番
- 蕃
- 朋
- 倍
- 抱
- 褒
- 裒
- 陪
- 報
- 袍
- 譜
- 穂
- 火
- 帆
- ぼ
- 煩
- ま
- 麻
- 磨
- 万
- 馬
- 末
- 摩
- 満
- 麼
- 莽
- 魔
- 真
- 間
- 目
- 鬼
- み甲
- 弥
- 美
- 民
- 瀰
- 湄
- 弭
- 寐
- 三
- 御
- 見
- 水
- 参
- 視
- み乙
- 未
- 味
- 尾
- 微
- 身
- 実
- 箕
- む
- 牟
- 武
- 无
- 模
- 務
- 無
- 謀

- 鵡
- 霧
- 夢
- 茂
- 六
- め甲
- 売
- 咩
- 馬
- 面
- 謎
- 迷
- 綿
- 女
- め乙
- 米
- 梅
- 迷
- 昧
- 毎
- 妹
- 目
- 眼
- も
- 毛
- 母
- 茂
- 望
- 文
- 聞
- 忘
- 蒙
- 畝
- 問
- 門
- 勿
- 暮
- 謀
- 慕
- 謨
- 悶
- 墓
- 莽
- 物〔古事記では、「も甲—毛、も乙—母」〕
- 裳
- 藻
- 哭
- 喪
- や
- 移
- 夜
- 楊
- 陽
- 耶
- 益
- 野
- 也
- 椰

- 揶
- 屋
- 八
- 矢
- 箭
- ゆ
- 由
- 喩
- 遊
- 油
- 庾
- 踰
- 愈
- 瑜
- 臾
- 弓
- 湯
- え(ヤ行)
- 叡
- 延
- 曳
- 遥
- 要
- 兄
- 江
- 枝
- 吉
- よ甲
- 用
- 欲
- 容
- 庸
- 遥
- 夜
- よ乙
- 余
- 与
- 予
- 餘
- 預
- 誉
- 世
- 吉
- 四
- 代
- ら
- 羅
- 良
- 浪
- 邏

- 囉

- 濫
- 楽
- 等
- り
- 利
- 理
- 里
- 隣
- 梨
- 離
- 唎
- 釐
- る
- 留
- 流
- 琉
- 類
- 瑠
- 屢
- 藘
- 楼
- 漏
- 盧
- 婁
- れ
- 礼
- 例
- 列
- 烈
- 連
- 黎
- 戻
- ろ甲
- 漏
- 魯
- 婁
- 路
- 盧
- 楼
- 露
- ろ乙
- 里
- 呂
- 侶
- 慮
- 廬
- 稜
- わ
- 和
- 倭
- 涴
- 輪
- ゐ
- 韋
- 為
- 位
- 威
- 謂
- 萎
- 委
- 偉
- 井
- 猪
- 居
- ゑ
- 恵
- 廻
- 慧
- 佪
- 衛
- 隈
- 穢
- 画
- 坐
- 座
- 咲
- を
- 乎
- 袁
- 烏
- 曰
- 遠
- 怨
- 呼
- 鳴
- 塢
- 弘
- 惋
- 越
- 小
- 尾
- 少
- 麻
- 男
- 雄
- 緒
- 綬

 ページTopに戻る
ページTopに戻る