俳句と連句とを江戸時代には俳諧とよんだ。俳諧とは「俳諧の連歌」の略称である。中世に盛行した純正連歌の一異体で、純正連歌が和歌的優美さを志向したのに対し、滑稽・卑俗を狙った。
江戸時代になると、京都の松永貞徳を祖とする貞門俳諧が流行したが、微温的な笑いに変わった。貞徳没後は新興都市大坂の宗因・西鶴らを中心に反貞門俳諧として談林俳諧が勃興する。
元禄期には芭蕉によって高い文学性を持つ芭蕉俳諧がうちたてられた。その後芭蕉門下の支考・基角の亜流が喜ばれ俗化するが、安永・天明期には蕪村らが芭蕉に帰ることを唱えて中興運動を展開した。文化・文政期以後見るべき作者は少なく、成美や一茶を挙げうるにすぎない。
連歌
雪ながら山もと霞む夕かな宗祇
行く水遠く梅にほふ里肖柏
河風に一むら柳春見えて宗長
舟さす音もしるき明けがた祇
月や猶霧わたる夜に残るらん柏
霜おく野原秋は暮れけり長
鳴く虫の心ともなく草かれて祇
垣根をとへばあらはなる路柏
(長享二2年「水無瀬三吟百韻」表八句)
室町期の俳諧
くろきものこそ
なかに子が左みぎりはおやがらす
まくらの上の駒の足音
宇治橋の下に今夜は泊まり舟
「竹馬狂吟集」
霞の衣すそはぬれけり
佐保姫の春立ながら
阿弥陀は浪の底にこそなれ
南無と言ふ声のうちより身を投げて
「誹諧連歌抄」(犬竹波集)
われも〱のからすうぐひす
のどかなる風ふくろうに山見えて
目もとすさまじ月のこるかげ
あさがほの花のしけくやしほるらん
これ重宝の松のつゆけさ
むら雨のあとにつなげる馬の
かたつぶりかと夕暮のそら
「守武千句」(飛梅千句)第一(表八句)
貞門の時代
- 霞さへまだらに立つやとらの年貞徳
- 花よりも団子やありて帰る雁貞徳
- 順礼の棒ばかり行く夏野かな重頼
- これはこれはとばかり花の吉野山貞室
- 松にすめ月も三五夜中納言貞室
- 一僕とぼくぼくありく花見かな季吟
- まざまざといますが如し魂祭り季吟
- 春立つやにほんでめたき門の松徳元
- 雪の朝二の字二の字の下駄のあと捨女
談林の時代
- 世の中や蝶々とまれかくもあれ宗因
- 今こんといひしば雁の料理かな宗因
- 長持へ春ぞくれ行く
更衣 西鶴 - 大晦日定めなき世のさだめかな西鶴
芭蕉の時代
- 木枯の果てはありけり海の音言水
- 菜の花や淀も桂も忘れ水言水
- 夕暮れのものうき雲やいかのぼり才麿
- 笹折りて白魚のたえだえ青し才麿
- 春の水ところどころに見ゆるかな鬼貫
- 行水の捨所なき虫の声鬼貫
- 白魚やさながら動く水の色来山
- 幾秋かなぐさめかねつ母ひとり来山
- 目には青葉山ほとゝぎすはつ鰹素堂
- 日の春をさすがに鶴の歩みかな其角
- 越後屋にきぬさく音や
衣更 其角 - ふとん著て寝たる姿や東山嵐雪
- むめ一輪一りんほどのあたゝかさ嵐雪
- おうおうといへど
敲 くや雪の門 去来 - 岩はなやここにもひとり月の客去来
- 大原や蝶の出て舞ふ朧月丈草
- 水底を見て来た顔の小鴨かな丈草
- ふり上ぐる
鍬 の光りや春の野ら杉風 - こがらしに二日の月の吹き散るか荷兮
- 雁が音もしづかに聞けばからびずや越人
- 市中は物のにほひや夏の月凡兆
- 下京や雪つむ上の夜の雨凡兆
十団子 も小粒になりぬ秋の風許六- 鳥どもも寝入ってゐか余吾の海路通
- ほのぼのと鳥黒むや窓の春野坂
- 船頭の耳の遠さよ桃の花支考
蕪村の時代
- 朝顔につるべとられて
貰 ひ水千代女 - 春の海
終日 のたり〱かな蕪村 - 不二ひとつ埋み残して若葉かな蕪村
- 菜の花や月は東に日は西に蕪村
- 愁ひつつ岡にのぼれば花いばら蕪村
- さみだれや大河を前に家二軒蕪村
高麗舟 の寄らで過ぎゆく霞かな蕪村- やぶ入りの寝るやひとりの親の
側 太祇 傘 の上は月夜のしぐれかな召波- 初時雨真昼の道をぬらしけり大魯
- やはらかに人分け行くや
勝角力 几董 - 枯芦の日に日に折れて流れけり闌更
- 世の中は三日見ぬ間に桜かな蓼太
- 火ともせばうら梅がちに見ゆるなり暁台
- 人恋し灯ともしころをさくらちる白雄
- あらし吹く草の中よりけふの月樗良
化政時代
- 魚食うて口なまぐさし昼の雪成美
- ゆさゆさと桜もて来る月夜かな道彦
- こがらしや日に日に
鴛鴦 の美しき士朗 - 是がまあつひの栖か雪五尺一茶
- 痩蛙まけるな一茶是にあり一茶
- めでたさも中位なりおらが春一茶
- 冬の夜や針うしなうておそろしき梅室
歌仙
| 初折表 | 牛流す村の騒ぎや |
諷竹 | 発句 | 夏 |
| 青葉ふき切る |
去来 | 脇 | 夏 | |
| 一枚の |
芭蕉 | 第三 | 雑 | |
| つかもこじりも古き脇差し | 惟然 | 雑 | ||
| 月影に |
丈草 | 冬・月 | ||
| 堤おりては田の中の道 | 支考 | 雑 | ||
| 初折裏 | 家〱はなよ竹原の間にて | 来 | 雑 | |
| お |
竹 | 雑 | ||
| 秋もやゝ今朝から寒き |
然 | 秋 | ||
| 野明 | 秋 | |||
| 抱き込んで松山広き有明に | 考 | 秋・月 | ||
| あふ人ごとの魚くさきなり | 蕉 | 雑 | ||
| 雨乞のしぶりながらに降り出して | 草 | 夏 | ||
| 然 | 夏 | |||
| 極楽でよい居所を頼みやり | 竹 | 雑 | ||
| 来 | 雑 | |||
| 道もなき畠の |
草 | 春・花 | ||
| 考 | 春 | |||
| 名残折表 | 川船の濁りにくだすうす霞 | 明 | 春 | |
| 塔にのぼりて消るしら雲 | 然 | 雑 | ||
| 売りに出す竹の子掘つて惜しむらん | 考 | 夏 | ||
| 茶どきの雨の迷惑な |
竹 | 夏 | ||
| このごろの |
来 | 雑 | ||
| 腰に杖さす |
蕉 | 雑 | ||
| わらぶきに |
然 | 秋 | ||
| ちら〱鳥の渡り初めけり | 明 | 秋 | ||
| 朝の月起き〱たばこ五六服 | 竹 | 秋・月 | ||
| 来 | 雑・恋 | |||
| 蕉 | 雑 | |||
| 加減をせゝる浅漬けの桶 | 然 | 雑 | ||
| 名残折裏 | 出来て来る青の |
明 | 雑 | |
| 何をけら〱笑ふ髪結ひ | 竹 | 雑 | ||
| 来 | 雑 | |||
| 蕉 | 雑 | |||
| 然 | 春・花 | |||
| 日ぐせになりし春のあめかぜ | 明 | 挙句 | 春 |
(元禄七年「牛流す」歌仙)
芭蕉
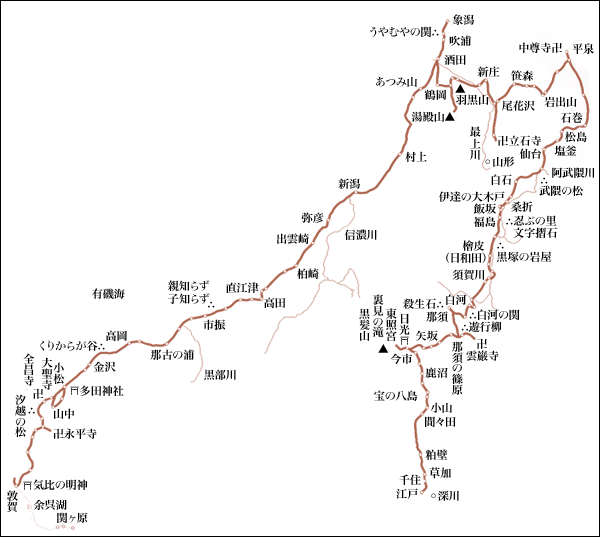
おくのほそ道
- 千住行く春や鳥啼き魚の目は泪
- 日光あらたうと青葉青葉の日の光
- 裏見の滝暫時は瀧に籠るや
夏 の初め - 那須野を横に馬牽きむけよほととぎす
- 黒羽夏山に足駄を拝む
首途 哉 - 雲巌寺
木啄 も庵は破らず夏木立 - 遊行柳田一枚植ゑて立ち去る柳かな
- 白河関卯の花をかざしに関の晴着かな 曾良
- 須賀川風流の初めやおくの田植うた
- 忍ぶの里早苗取る手もとや昔しのぶ摺
- 飯塚笈も太刀も五月にかざれ
紙幟 - 武隈の松桜より松は
二木 を三月越し - 笠島笠島はいづこ五月のぬかり道
- 仙台あやめ草足に結ばん
草蛙 の緒 - 松島松島や鶴に身を借れほととぎす 曾良
- 高館夏草や
兵 共がゆめの跡 - 光堂五月雨のふり残してや光堂
尿前 関蚤虱馬の尿 する枕もと- 尾花沢涼しさをわが宿にしてねまるなり
- 〃眉掃きを俤にして
紅粉 の花 - 立石寺しづかさや岩にしみ入る蝉の声
- 白糸の滝五月雨をあつめて早し最上川
- 羽黒山涼しさやほの三日月の羽黒山
- 月山雲の峰いくつ崩れて月の山
- 湯殿山語られぬ湯殿にぬらす袂かな
- 酒田暑き日を海に入れたり最上川
- 〃あつみ山や吹浦かけて夕涼み
- 象潟
象潟 や雨に西施がねぶの花 - 出雲崎荒海や佐渡に横たふ天の川
- 市振一つ家に遊女も寝たり萩の月
- 有磯海早稲の香や分け入る右は有磯海
- 金沢塚も動けわが泣く声は秋の風
- 〃あか〱と日は
難面 も秋の風 - 多田神社むざんやな
甲 の下のきりぎりす - 那谷石山の石より白し秋の風
- 山中山中や菊はたをらぬ湯の匂ひ
- 全昌寺庭掃きて出でばや寺に散る柳
- 松岡物書きて扇引きさくなごりかな
- 気比の明神月清し遊行の持てる砂の上
- 敦賀名月や北国日和定めなき
- 種の浜波の間や小貝にまじる萩の塵
- 大垣蛤のふたみに別れ行く秋ぞ
野ざらし紀行・笈の小文等
(「野ざらし紀行」)
- 深川野ざらしを心に風のしむ身かな
- 足柄関霧しぐれ富士を見ぬ日ぞ面白き
- 富士川猿を聞く人捨子に秋の風いかに
- 小夜中山馬に寝て残夢月遠し茶の煙
- 伊勢神宮
三十日 月なし千年 の杉を抱くあらし - 竹の内綿弓や琵琶に慰む竹の奥
- 二上山当麻寺僧朝顔幾死に返る
法 の松 - 吉野霧とく〱心みに浮世すすがばや
- 不破関秋風や藪も畠も不破の関
- 大垣死にもせぬ旅寝の果てよ秋の暮
- 桑名明けぼのやしら魚白きこと一寸
- 熱田神宮しのぶさへ枯て餅買ふやどり哉
- 名古屋狂句木枯の身は竹斎に似たる哉
- 〃草枕犬もしぐるゝか夜の声
- 熱田海くれて鴨の声ほのかに白し
- 伊賀上野年暮れぬ笠きて
草蛙 はきながら - 奈良二月堂水取りや氷の僧の
沓 の音 - 鳴瀧梅白し昨日や鶴を盗まれし
- 伏見我が
衣 に伏見の桃の雫 せよ - 京—大津山路来て何やらゆかしすみれ草
- 辛崎
辛崎 の松は花よりおぼろにて - 水口命二つ中に生きたる桜哉
(「笈の小文」)
- 鳴海星崎の闇を見よとや
啼 く千鳥 - 吉田寒けれど二人寝る夜ぞ頼もしき
- 天津なわて冬の日や馬上に凍る影法師
- 伊良古崎鷹一つ見付けてうれしいらご崎
- 杖つき坂
歩行 ならば杖 つき坂を落馬哉 - 伊賀上野旧里や
臍 の緒に泣くとしの暮れ - 〃さまざまの事思ひ出す桜哉
- 新大仏寺丈六にかげろふ高し石の上
- 宇治山田何の木の花とは知らず匂ひ哉
- 吉野山吉野にて桜見せうぞ檜の木笠
- 初瀬春の夜や籠り
人 ゆかし堂の隅 - 葛城山なほ見たし花に明けゆく神の顔
- 細峠
雲雀 より上に休らふ峠哉 - 龍門龍門の花や上戸の
土産 にせん - 西河ほろ〱と山吹ちるか瀧の音
- 高野父母のしきりに恋し
雉 の声 - 奈良灌仏の日に生まれあふ
鹿 の子哉 - 唐招提寺若葉して御目の
雫 ぬぐはばや - 八木草臥て宿かる比や藤の花
- 須磨須磨寺やふかぬ笛きく
木下 闇 - 和歌の浦行く春にわかの浦にて追ひ付きたり
- 明石蛸壺やはかなき夢を夏の月
(「更級紀行」)
- かけはし
棧 やいのちをからむつたからづら - 更科の里
俤 や姨 ひとり泣く月の友 - 善光寺月影や四門四宗も只一つ
- 浅間山吹きとばす石は浅間の野分哉
各地の芭蕉
- 深川芭蕉野分して
盥 に雨を聞く夜かな - 〃花の雲鐘は上野か浅草歟
- 鹿島月はやし梢は雨を待ちながら(「鹿島詣」)
- 長良川おもしろうてやがてかなしき鵜舟かな
- 木曾送られつおくりつ果ては木曾の秋
- 京都長嘯の墓もめぐるか鉢たたき
- 大津少将のあまの
咄 や志賀の雪 - 琵琶湖行春を近江の人とをしみける
- 義仲寺明日や座にうつくしき
 もなし
もなし - 堅田病雁の夜寒に落ちて旅寝かな
- 〃海士の屋は小海老にまじるいとどかな
- 伊賀上野山里は万歳遅し梅の花
- 嵯峨ほととぎす大竹藪をもる月夜
- 〃うき我をさびしがらせよかんこ鳥
- 垂井
葱 白く洗ひたてたるさむさ哉 - 江戸鎌倉を生きて出でけむ初鰹
- 川崎麦の穂を便りにつかむ別れかな
- 駿河路するが路や花橘も茶の匂ひ
- 大井川さみだれの空吹きおとせ大井川
- 佐屋
水鶏 啼くと人のいへばや佐屋泊り - 嵯峨六月や峰に雲置くあらし山
- 清滝清滝や波に散りこむ青葉松
- 奈良びいと啼く尻声悲し夜の鹿
- 〃菊の香や奈良には古き仏達
- 大坂此道や行く人なしに秋の暮
- 〃秋深き隣は何をするひとぞ
- 〃旅に病で夢は枯れ野をかけ廻る
 ページTopに戻る
ページTopに戻る