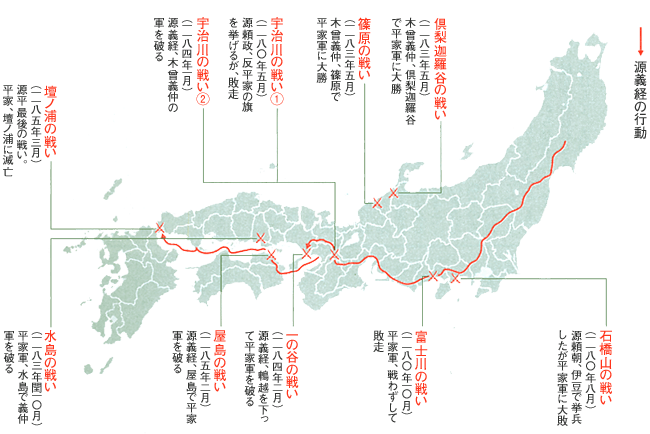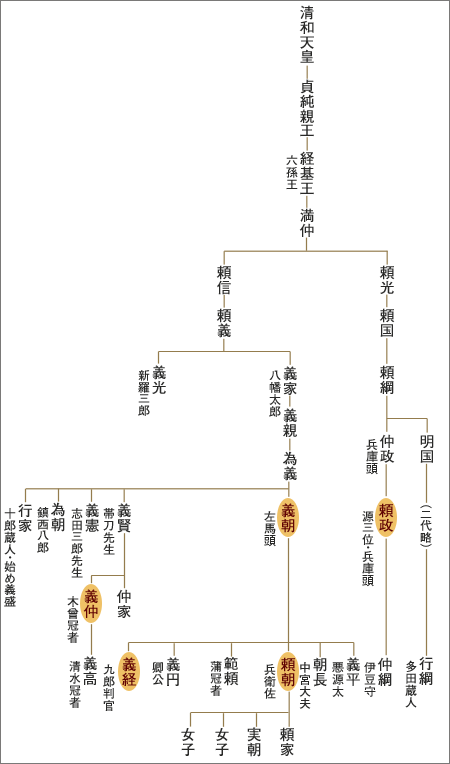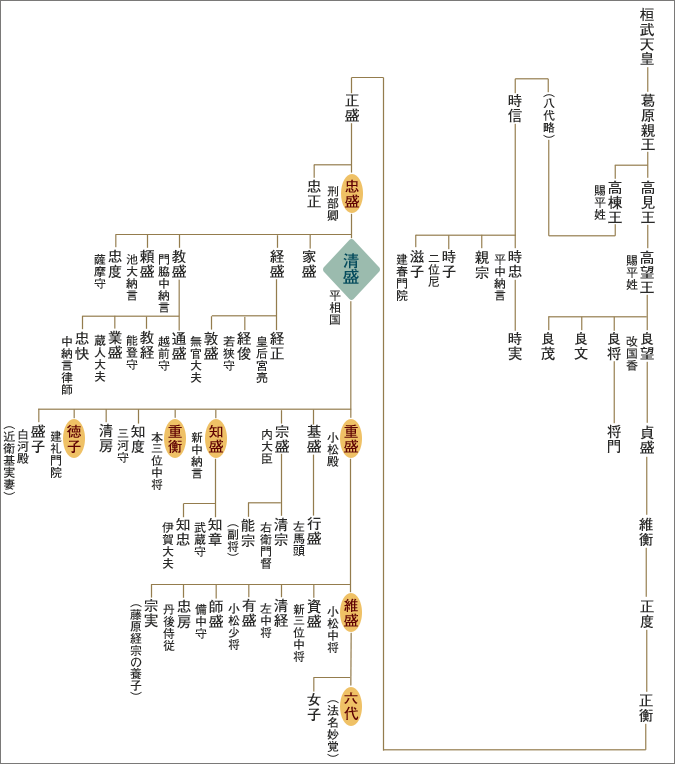物語
鎌倉前期の軍記物語。平清盛を中心とする平家一門のめざましい興隆と栄華、政権の座からの転落滅亡の過程を、平治の乱(一一五九1159年)以後の清盛の擡頭から、元暦二2年(一一八五1185)の壇ノ浦における平家滅亡、残された建礼門院徳子の往生(建久二2年〈一一九一1191〉)に至るおよそ三〇30年に焦点をあてて描く。
頂点を極めるも、数々の悪行をなし、熱病に冒されて「あつち死に」する清盛。物語は以後、清盛の悪行の報いを受けるが如くの平家の公達の「生」と「死」を描いていく。死に直面してなお恩愛のはざまに揺れる維盛、「見るべき程の事は見つ」と言い、鎧を二領重ねて壇ノ浦に沈んだ知盛などが克明に描かれる。また、抜群の戦略家であった源義経、一旦は都を占拠したものの惨めに追われていく木曾義仲など、一方の源氏の大将たちにも多くの筆をさく。清盛の寵愛を受けた祇王や仏御前、滝口入道と悲恋の主人公横笛など、処々に織り込まれる恋愛・風流談も物語の眼目である。武士の時代の到来という一大転換期を生きる人物が生き生きと、時に哀感をもって語られている。諸行無常・盛者必衰の無常観、厭離穢土・欣求浄土の仏教浄土教の思想が全編を覆い、スケールの大きな物語を形成している。
成立は一三13世紀半ば頃とされる。「徒然草」に信濃の前司行長が作り、生仏に語らせたと伝えるが、成立の真相は不明である。平家物語が人々に広く浸透していったのは、琵琶法師が全国を語って歩いたのに負うところが大きい。
平家物語には多くの異本が伝わり、琵琶法師や寺院の説教師、さらには知識人らによって、多様な物語が構成し続けられたことがうかがわれる。現在最も一般的な本文「覚一本」は平家の興亡を描く一二12巻に、建礼門院の往生を記す灌頂巻を付している。琵琶法師覚一が語りの台本として定めたもので、典型的な和漢混交文で叙され、文芸的に最も完成したものとして評価が高い。この他、古態を残すと言われる「延慶本」、記事が広汎に膨れあがっている「源平盛衰記」(四八48巻)、変体漢文で記される「四部合戦状本」など、読むことに主眼をおいて生成したと見られる本もある。
諸本により記事内容も異なり、名称を異にするものもあるが、これらが平家物語と総称されるのは、すべての本が「祇園精舎の鐘の声諸行無常の響あり」の句で始まり、清盛の曾孫六代の斬られ(断絶平家)、または建礼門院の往生(灌頂巻)で終わることにある。
 ページTopに戻る
ページTopに戻る