第一部
| 光源氏年齢 | 巻名 | 主要事項 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一~一二1~12歳 | 1 |
光源氏誕生。 母桐壺更衣死去。光源氏臣籍降下。藤壺入内。 源氏元服。葵上と結婚。 |
||
| 一三~一六13~16歳 | [この間、四年間が経過] | |||
| 一七17歳 | 2 |
<雨夜の品定め>源氏、空 に会う。 に会う。 |
||
3 |
空 、源氏を拒む。 、源氏を拒む。 |
|||
| 4 |
夕顔との恋。秋、夕顔死去。 | |||
| 一八18歳 | 5 |
源氏、紫上を発見。 自邸に引き取る。 源氏、藤壺と契る。 藤壺、懐妊。 |
6 7 |
源氏、末摘花に通う。 雪の朝、その醜貌に驚く。 源氏、試楽で青海波を舞う。 冷泉帝誕生。 |
| 一九19歳 | ||||
| 二〇20歳 | 8 |
源氏、朧月夜に会う。 | ||
| 二一21歳 | [この間に桐壺帝譲位。朱雀帝即位] | |||
| 二二22歳 | 9 |
御禊の日、葵上と六条御息所の従者、車の立所をめぐり争う。 六条御息所の生霊出現。葵上、夕霧を出産後、死去。 源氏、紫上と新枕を交わす。 |
||
| 二三23歳 | 10 |
秋、御息所、伊勢に下向。冬、桐壺帝崩御。 | ||
| 二四24歳 | 源氏、藤壺に迫る。藤壺、出家。 | |||
| 二五25歳 | 朧月夜との密会発覚。 | 11 |
源氏、花散里を訪う。 | |
| 二六26歳 | 12 |
源氏、須磨に下向。須磨でのわび住まい。 | ||
| 二七27歳 | 13 |
源氏、明石に移る。秋、明石君と契りを交わす。 | ||
| 二八28歳 | 源氏、帰京。 政界復帰。 |
15 |
末摘花、窮乏生活に耐えつつ源氏を待つ。 | |
| 二九29歳 | 14 |
朱雀帝譲位。冷泉帝即位。 | ||
| 明石姫君誕生。 | 源氏、末摘花と再会。 | |||
| 六条御息所帰京、娘を源氏に託して他界。 | 16 |
源氏、逢坂の関で空 一行と出会う。 一行と出会う。 |
||
| 三〇30歳 | ||||
| 三一31歳 | 17 |
六条御息所の娘、冷泉帝に入内。帝の御前で絵合が催される。 | ||
| 18 |
明石君、姫君と上京。 | |||
| 三二32歳 | 19 |
藤壺、崩御。冷泉帝、出生の秘密を知る。 | ||
| 20 |
源氏、朝顔姫君に求婚。朝顔、拒否する。 | |||
| 三三33歳 | 21 |
<教育論>夕霧と雲居雁の恋。 | ||
| 三四34歳 | 夕霧、進士に及第。 | |||
| 三五35歳 | 22 |
玉鬘、筑紫から上京。源氏に引き取られる。 | ||
| 秋、六条院完成。 <春秋争い> |
<歌論> | |||
| 三六36歳 | 23 |
六条院の新春。 | ||
| 24 |
玉鬘と求婚者たちの恋愛模様。源氏、玉鬘に惹かれる。 | |||
| 25 |
兵部卿宮、蛍の光で玉鬘を見る。 <物語論> |
|||
| 26 |
近江君、世間の噂になる。 | |||
| 27 |
源氏、玉鬘への思いに悩む。 | |||
| 28 |
野分の朝、夕霧、紫上を垣間見て、その美しさに驚く。 | |||
| 三七37歳 | 29 |
玉鬘、裳着。その日、実の父内大臣と対面。 | ||
| 30 |
髭黒大将、玉鬘に熱心に言い寄る。 | |||
| 31 |
髭黒大将、玉鬘を得る。大将の北の方、嫉妬。 玉鬘、尚侍として参内の後、髭黒大将の自邸に引き取られる。 |
|||
| 三八38歳 | ||||
| 三九39歳 | 32 |
<薫物合わせ> 明石姫君、裳着。 |
||
| 33 |
夕霧、雲居雁と結婚。明石姫君、東宮に入内。 源氏、准太上天皇となる。 |
|||
第二部
| 光源氏年齢 | 巻名 | 主要事項 |
|---|---|---|
| 三九39歳 | 34 |
朱雀院、女三宮の処遇を苦慮。 |
| 四〇40歳 | 女三宮、源氏に降嫁。紫上、苦悩する。 源氏の四十賀、次々に催される。 |
|
| 四一41歳 | 春、蹴鞠遊びの日、柏木、女三宮を垣間見る。 | |
| 35 |
柏木、女三宮への恋慕の思いを募らせる。 | |
| 四二~四五42~45歳 | 〔この間、四年間記事なし〕 | |
| 四六46歳 | 冷泉帝、譲位。今上帝即位。 源氏、住吉に詣でる。明石女御・紫上など同行。 |
|
| 四七47歳 | 六条院での女楽。紫上発病。柏木、女三宮と契る。 六条御息所の死霊出現。源氏、柏木と女三宮の密事を知る。 |
|
| 四八48歳 | 36 |
女三宮、薫を出産、出家。柏木、夕霧に後事を託して死去。 |
| 四九49歳 | 37 |
夕霧、柏木未亡人の落葉宮を訪う。 |
| 五〇50歳 | 38 |
源氏、女三宮のもとで鈴虫の宴。 |
| 39 |
夕霧と落葉宮の関係を源氏憂慮。紫上、女の生き難さを思う。 夕霧、落葉宮を得る。 |
|
| 五一51歳 | 40 |
紫上死去。 |
| 五二52歳 | 41 |
源氏、紫上を追悼。悲しみの一年を過ごす。 |
第三部
| 薫年齢 | 巻名 | 主要事項 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一四14歳 一五~一九15~19歳 |
42 |
薫、元服。 薫、自分の出生に疑念を抱く。 |
44 |
髭黒他界後の玉鬘一家の様子と姫君たちの縁談。 |
| 二〇20歳 | 45 |
薫、宇治の八宮のもとに通い始める。 | ||
| 二一21歳 | ||||
| 二二22歳 | 薫、宇治の大君・中君を垣間見る。 薫、出生の秘事を知る。 |
|||
| 二三23歳 | 46 |
八宮、姫君たちに訓戒を残して他界。 | ||
| 二四24歳 | 43 |
49 今上帝、薫に女ニ宮との縁組をほのめかす。 匂宮、夕霧家の六君と結婚。 薫、中君に思いを寄せる。匂宮、二人の仲を疑う。 薫、女ニ宮と結婚。 |
||
| 47 |
大君、薫の求愛を拒む。 匂宮、中君と契る。 大君、発病。死去。 |
|||
| 二五25歳 | 48 |
中君、上京。匂宮の二条院に移る。 | ||
| 二六26歳 | 50 |
浮舟、登場。 | ||
| 二七27歳 | 51 |
浮舟、薫と匂宮の愛に苦しむ。入水を決意。 | ||
| 52 |
人々、浮舟の失踪を悲しむ。 | 53 |
浮舟、横川の僧都に助けられる。素姓を隠したまま出家。 | |
| 二八28歳 | 54 |
薫、浮舟の生存を知り、浮舟に消息を送る。 | ||
解説
平安中期の長編物語。五四54巻。作者は紫式部。 成立年は未詳だが、紫式部が夫の藤原宣孝に死別した長保三3年(一〇〇一1001)以降、 中宮彰子に出仕したとされる寛弘二2年(一〇〇五1005)までの間に起筆され、 宮仕え後も書き続けられたのではないかと推測されている。 五四54巻の執筆順序についても、さまざまな説が出されており、作者についても、 とくに宇治十帖に先立つ「匂宮」「紅梅」「竹河」三3巻に関しては、人物の官名や年立に矛盾が見えるところから、 別人作とする説もあるが、いずれも確かなことはわかっていない。
物語は、四代の帝、七十数年にわたって展開する。 主だった登場人物だけでも四〇40人を超え、作中歌も七九五795首を数えるという壮大な作品だが、 主題と構造の面から、物語全体を三部に区切って理解する三部構成説が有力である。 第一部は「桐壺」から「藤裏葉」に至る三三33巻で、光源氏の誕生から、数々の恋の遍歴や須磨流謫などを経て、 源氏が准太上天皇という栄光の地位に就くまでの物語。 第二部は「若菜上」から「幻」までの八8巻、正妻女三宮の密通や紫上の病など、深い内面の苦悩が描かれる。 第三部は「匂宮」から最終「夢浮橋」までの一三13巻で、源氏没後、主人公となる青年薫を中心に、救済を求めて、 愛と道心の間で迷い葛藤する人々の姿が追及されている。
登場人物系図
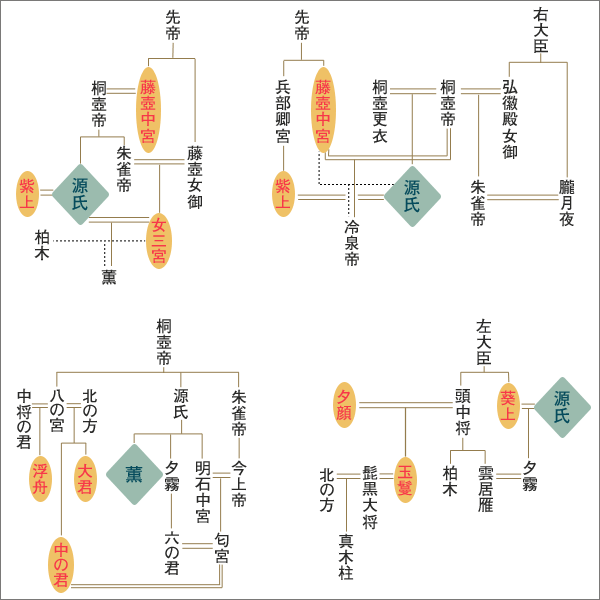
物語
第一部(1桐壺~33藤裏葉)
桐壺更衣は、帝の寵愛を受けて輝くばかりに愛らしい男御子(第二皇子)をもうけたが、
低い身分のために周囲の嫉妬や迫害はきびしく、御子が三3歳になった年、心労が積もって他界した。
この皇子の比類ない資質が、将来世の乱れを招きかねないと案じた帝は、
彼に源氏姓を与え、臣籍に降下させた1。
これが物語の主人公「光源氏」である。
第一部は、亡き母によく似るとされる桐壺帝の后藤壺への禁じられた恋と、
藤壺のゆかりとして登場する可憐な少女紫上への愛を軸として、葵上、空 、夕顔、六条御息所、
末摘花、朧月夜、花散里、明石君、朝顔、玉鬘といった女性たちとの恋の遍歴が語られてゆく。
藤壺との密通5と不義の皇子(後の冷泉帝)の誕生7、
六条御息所の物の怪と正妻葵上の死9、
政敵右大臣の娘朧月夜との密会810
とそれを契機とした須磨への退去12、
明石君との邂逅13と姫君の誕生など、さまざまな事件の後、
政界に復帰した源氏は、即位した冷泉帝の後見役として、絶対的な権勢への道を歩んでゆく14。
四町を占めて造営された広大な六条院は、それぞれに四季の風情を配し、春の町に紫上、夏の町に花散里、
秋の町に秋好中宮(六条御息所の娘。冷泉帝中宮)、冬の町に明石君を住まわせ、現世の極楽を思わせる華麗なものであった21。
その六条院を舞台に繰り広げられる玉鬘(夕顔の遺児)の恋愛模様22~31
を語った後、物語は、夕霧の結婚、明石姫君の東宮入内、史実上にも前例のない准太上天皇への源氏の昇進、
冷泉帝と朱雀院の六条院行幸という、極まりない栄華を描いて一段落する33。
、夕顔、六条御息所、
末摘花、朧月夜、花散里、明石君、朝顔、玉鬘といった女性たちとの恋の遍歴が語られてゆく。
藤壺との密通5と不義の皇子(後の冷泉帝)の誕生7、
六条御息所の物の怪と正妻葵上の死9、
政敵右大臣の娘朧月夜との密会810
とそれを契機とした須磨への退去12、
明石君との邂逅13と姫君の誕生など、さまざまな事件の後、
政界に復帰した源氏は、即位した冷泉帝の後見役として、絶対的な権勢への道を歩んでゆく14。
四町を占めて造営された広大な六条院は、それぞれに四季の風情を配し、春の町に紫上、夏の町に花散里、
秋の町に秋好中宮(六条御息所の娘。冷泉帝中宮)、冬の町に明石君を住まわせ、現世の極楽を思わせる華麗なものであった21。
その六条院を舞台に繰り広げられる玉鬘(夕顔の遺児)の恋愛模様22~31
を語った後、物語は、夕霧の結婚、明石姫君の東宮入内、史実上にも前例のない准太上天皇への源氏の昇進、
冷泉帝と朱雀院の六条院行幸という、極まりない栄華を描いて一段落する33。
第二部(34若菜上~41幻)
「若菜上」巻は、源氏が、朱雀院の懇請により、院の最愛の姫であり、 藤壺の姪にもあたる女三宮を正妻として迎えるに至るいきさつから語り出される。 六条院に降嫁した女三宮は、藤壺ゆかりの人への源氏の秘かな期待に反して幼稚な姫君であった。 この結婚によって源氏はあらためて紫上のすばらしさを確認し愛を強めるが、 六条院の女主人としての立場を失うことになった紫上の苦悩は深く、源氏への不信感と孤独感から切実に出家を願うようになる。 一方、かねてから女三宮との結婚を望んでいた柏木は、六条院での蹴鞠の折、偶然宮の姿を垣間見て以来、 いよいよ恋慕の思いを募らせていた34。 朱雀院五十の賀の年、賀宴に先立って、源氏は女君たちによる試楽を催したが、 その夜、心労の重なった紫上は発病、源氏は懸命の看護を尽くした。 そうした中で、柏木と女三宮の密通事件が起こる。 真相を知って苦悩する源氏、源氏に対して恐れおののく柏木と女三宮、病の床に臥す紫上35。 そこには第一部に描かれた栄光の世界はない。女三宮は罪の子薫を出産すると、朱雀院に懇願して出家。 柏木も後事を親友の夕霧に託して他界する36。 女の生きがたさを痛感し、出家を望みながら、源氏のために最後まで実現できなかった紫上も、 人々に惜しまれつつ遂にこの世を去る40。 最愛の人に先立たれた源氏は、深い悲しみと孤独のうちに出家を思う41。
古来、「幻」と「匂宮」の巻の間に「雲隠」という巻名が伝わっているが、本文は伝存しない。
第三部(42匂宮~54夢浮橋)
「匂宮」巻は「光隠れたまひし後」と書き出され、物語は源氏の次代に移っている。 薫はすでに一四14歳、匂宮(明石姫君腹。源氏の孫にあたる)とともに世に並び称される貴公子だが、 自分の出生への疑念に苦しんでいた42。 若くして出離の志を持ち、宇治に隠棲する俗聖八の宮を慕って宇治に通ううちに、 宮の娘大君と中君を知り、なかでも大君に強く惹かれてゆく45。 八の宮の没後、大君にその思いを訴えるが、父の遺戒を守る大君は薫の愛を固く拒み、 自分の代わりに薫と妹を結婚させようとする。 大君の考えを知った薫は、匂宮を中君に通わせるが、今上帝の三の宮である匂宮は、 夕霧大臣家に六の君の婿として迎えられることになった。 裏切られた思いの大君は、不信と屈辱感のうちに死去する4647。 大君を忘れられない薫は、中君を匂宮に譲ったことを後悔するが48、 中君から大君に似た異母妹浮舟の存在を聞き知り49、 亡き大君のゆかりとして宇治に住まわせた50。 しかし、匂宮も浮舟に関心を持つと、薫の目を盗んで宇治を訪れ、強引で情熱的な仕方で、 浮舟を自分のものにしようとする。 ふたりの貴公子の板ばさみとなった浮舟は、ひそかに宇治川への入水を決意する。51。 失踪後、倒れているところを横川の僧都に助けられた浮舟は、再び現世の愛欲の世界に戻ることを恐れて、 僧都に懇願して出家を果たし、仏道修行の日々を送る53。 浮舟生存を知った薫は、浮舟の弟を使者に遣わすが、浮舟は会おうとさえしなかった54。
物語はその先に多くの問題を抱えたまま、浮舟の態度を不審に思う薫を描いて終わっている。
本文
桐壺の巻
いづれの
有名な「源氏物語」の冒頭文。物語は、主人公光源氏の父桐壺帝と母桐壺更衣との悲恋から語り始める。 紫式部の手になるこの書き出しは、それまでの物語が常套として用いていた 「今は昔・・・」「昔・・・」という起筆形式を大きく打ち破る、文学史上画期的なものであった。 以後、物語作者たちは、冒頭の表現にさまざまな創意工夫を凝らすようになっていった。
 ページTopに戻る
ページTopに戻る